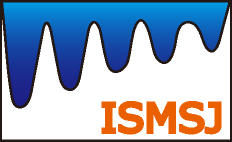第10回 ウィリアム・オスラーはやはりどこまでも偉い。
2012 年 5 月 1 日
テキサス州ヒューストン メソジスト病院
神経内科神経生理部門 河合 真
子育てに追われているうちに前回から随分間隔が空いてしまって申し訳ない。その間いろいろあったが、その中でも印象的だったことを話したいと思う。
さて、皆さんはどんな外来トレーニングを受けただろう?アメリカのよくあるスタイルはレジデントと呼ばれる研修医やフェローと呼ばれるレジデンシーを修了してより専門のトレーニングを受けている医師がまず一人で病歴聴取と診察をしてそのあと指導医にプレゼンし、そのあとで指導医が偉そうにレジデントとフェローを引き連れて登場し診療するというものである。大変時間がかかるので(新患だと1時間はかかる)日本の忙しい外来では無理だろう。ただ、トレーニング中の医師の診療に時間がかかるのは「仕方がない」と考えられており、余計にクリニックの枠が設定されている。もちろん、それが許されるのはトレーニング中の医師だけで、指導医は同時進行で数をこなしていくことが必要とされる。
時折レジデントやフェローが患者さんともめたりするが、それを治めるのも指導医の仕事である。トレーニング開始時の7月直後などは、結構患者さんとトラブルになることもあるが、半年たち年が明けるころには、おどおどしていたレジデントやフェローも堂々としてトラブルもなくなってくる。教えられるだけでなく、戦力として計算できるようになるので指導医としてもまかせていくようになる。そんな2月の出来事である。
睡眠外来で、神経生理学フェローのK医師が前診察をしている部屋から「もういや、こんな医者と話しても時間の無駄。帰る。」という60歳の女性の患者さんの金切り声が聞こえてきた。フェローは必死になだめているが、どうやら「役不足」の感が否めない。というわけで「やれやれ仕方ないな」と「真打ち登場」とばかりに私が診察室に入り、「まあまあおちついてお話を聞かせてください」と切り出した。
ところが、ちょっと勝手がちがう。患者さんは「こんな連中に話をしたって無駄よ。全然話を聞いてくれない!」と怒るばかりで肝心の話をしてくれない。付き添っていた患者さんのお姉さんが「もう一回だけ話をしましょうよ」ととりなし、話を聞くことができた。だが、患者さんの話は要領を得ない。「A医師(前にかかっていた医師らしい)は全く話を聞いてくれなかった。へんな薬(クロナゼパム)を出すだけで全然よくならない。」という。さらに、話をきいていくと「歩いていて眠るのよ。おかしいでしょ。なんとかして。」ということをなんとか聞き出した。それからRestless legs syndromeはあるらしいが、それはドパミンアゴニストのプラミペキソールを処方されていて「全く問題ない。歩いていて眠るのをなんとかして!」とヒステリックな調子で話す。「ああ、sleep walkか」と思い大人のsleep walkは珍しいが、まずはsleep apneaの除外が必要になってくるので「睡眠検査をしましょう」と話すが、「そんなものは必要ない!だって眠ったら歩かないもの」という。「いやいや、お話を聞いているとsleep walkの疑いがあって、大人の場合はsleep apneaを除外、、、、」といった途端に「ほら、この医者もsleep walkって言った!全然話を聞いていない!私はsleep walkじゃない!」と叫び、「帰る!」といって帰り支度を始めてしまった。
この時点でフェローのK医師が「私のときもsleep walkという単語を言った途端こうなったんです。」と遅ればせながら耳打ちしてくる。「遅いよ!」と思いながらもsleep walkという言葉がどんな地雷を踏んだのかわからない私は唖然とした。しかし、このまま帰ってもらうわけにいかないので、再び「まあまあもう一回だけ、あと一回だけ話を聞かせてください。それで納得いかなかったら帰っていただいて結構です。お代も頂きません。」と私が最後の切り札フレーズを使い、話を聞かせてもらうことになった。本来は、自由意思に基づく診療なのだから、帰るという患者さんを引きとめるいわれはないのだが、私もこのまま訳のわからないまま終われないと意地になった。
しぶしぶ(本当にしぶしぶ)患者さんが繰り返すには、「私は歩いていて眠るの(walk, then sleep)!眠って歩くのではないの(Sleep walk)!さあ、あなたになんとかできるの?さもないと時間の無駄、帰るわよ!」
睡眠医学でこのように英語でいうところの「コーナーに追いつめられる」経験をすることはほとんどないが、このとき私の頭に閃いたことがあった。
「いったい何時頃に歩いていて眠るのですか?」「夕食の準備を台所でしていて突然眠ってしまうのよ。歩いていたと思ったら突然台所の床で眠ってしまうの」
なるほどsleep walkではなくwalk, then sleepだなと思い処方をよくみてみると、ドパミンアゴニストのプラミペキソールが3mg分3(アメリカ式にいうと1mg1日3回)で処方されていた。パーキンソン病では使う用量だが、RLSにとってはかなりの高用量である。
「わかりました。おそらくプラミペキソールの副作用ですから、薬を減らしましょう。とりあえず、1日1回夜のみにしましょう。」というと「そうなのよ。どんどんいろんな医者がこの薬を増やしていくものだからおかしいと思っていたのよ。」とあっさり同意してくれた。
翌週再診にきた患者さんは、打って変ってニコニコして、「おかげでよくなりました。あなたは素晴らしい医者だ。他の医者をやめてあなたにかかります。」云々と気持ちいいことを言ってくれる。お姉さんも、「性格も元にもどったんです。前はめちゃくちゃな買い物やらギャンブルをするものだから困っていたんです。」ニコニコして言う。「そんな話、聞いてないよ」とおもったが、「そうですか、よかったですね」とこちらもニコニコ。
さて、これはいったいどういう病態か?おわかりの皆さんもおられると思うが、これはドパミンアゴニストによるsleep attack(sudden onset of sleepとも言う)の病態である。確かに患者さんは真実を告げていた訳である。おまけとしてはpathological shopping(病的買い物), pathological gambling(病的ギャンブル)も併発しており、impulsive behaviorという衝動が抑えられない状態でクリニックにおいて爆発をしていたわけである。これらはすべてドパミンアゴニストの副作用である。なるほど病歴聴取が難しいわけである。診断一発問題解決となり、患者さんはよろこぶ、私はほっとする、めでたしめでたしなのだが、よく考えるとこのことから学ぶべきことがいろいろある。
まずは、このきわどいタイミングで診断をつけた自分をほめたいのだが、これは別に私が名医でもなんでもなく、ドパミンアゴニストの副作用を「知っていた」にすぎない。逆にいうと知らなければ、絶対に診断をつけることはできない。自分の処方する薬についてはやはり良く知らねばならない。決してRLSを簡単にドパミンアゴニストで治療できるなどと思ってならない。手痛い失敗をすることになる。
次にやはり脳は面白い。睡眠医学をしていると脳の病態を知らずして睡眠は診療できないという思いが強くなってくる。今回の症例は「ドパミンアゴニストでsleep attack, pathological shopping, pathological gambling, impulsive behaviorが生じました」とまとめられるが、では「なぜ」そんなことが起きるのか?と考えると非常に興味深い。
最後に今回は自分の知っている病態(sleep walk)に患者さんの訴え(walk, then sleep)をあてはめようとして見事に失敗した。Listen to your patient, he(今回はshe)is telling you a diagnosis.という言葉を残したウィリアム・オスラーはいつでも偉いのである。

今実はアメリカ神経学会でニューオーリンズに来ている。ニューオーリンズはジャズの町として有名だが、学会会場の近くにこんなカジノがある。

ギャンブルに全く興味のない私はこのエントランスをくぐることなく、まっすぐホテルに帰り、この原稿を書いている。これもドパミンのバランスがとれているおかげである。

マッチポンプとはまさにこのことであろう。カジノのパーキングにあったサインである。曰く、30分カジノでギャンブルをすれば駐車料金がタダになると宣伝しギャンブルを奨励しておいて、その下にギャンブル依存になった人用のホットラインが宣伝してある。ここまでくればあきれるのを通り越して清々しい。
RLSを一人の睡眠専門医が治療しようとしてsleep attackを引き起こし、それをまた別の睡眠専門医がみるなんてこととちょっと似ているような気がする。