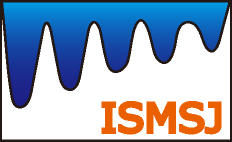第19回 クロスカバーと睡眠
2025 年 1 月 6 日
スタンフォード大学 睡眠医学センター
河合 真
突然だがあなたの同僚が担当している顧客が突然会社にクレームを入れてきたと想像して欲しい。そして折悪くその同僚が長期休暇中だったらどう対処するだろうか?
その場合の対処方法として以下のものがある。
1)「〇〇は休暇中ですので、私が変わって承ります。」
2)「〇〇は休暇中ですので、その件は全然わかりません。◯日に戻りますのでそれ以降に再度ご連絡ください。」
3)「〇〇は休暇中ですが、連絡をとって直接〇〇から連絡させるようにします。」
日本企業で多いパターンは1)が多いと思う。そして単純な文化比較をするのは心苦しいのだが、アメリカでは圧倒的に2)が多い。アメリカに渡った日本人が最初にアパートの契約などでこのような対応を受けて心が折れる。感じよく話が進んで、値引き交渉も済んで、さて最終契約をしようと思ったら相手が「いない」のだ。気を取り直して代わりの人と話をするが、2)で返信される。「おい、引き継ぎはどうなっているのだ!」と憤ってみても全く取りつく島もない。おそらくアメリカのセールスパースン達は個人の業績で評価されることが多いので、自分の顧客の情報を同僚に渡さないことも多く、本当にどうしようもない。それなら3)のように連絡が取れるようにしておいてくれ!と思うが休暇は休暇でメールも返信しない。結局担当者が休暇から帰ってくるのを待つか、別の担当者と1から交渉することになる。休暇から戻ってきた担当者に嫌味の一つも言いたいが、アメリカの社会では「休暇明けの労働者には休暇の楽しい話題で世間話をする」という不文律の常識がある。気分良く「あー、リフレッシュした。」みたいな顔をしている彼らに文句もなかなか言えない。まさに、社会として「休暇」が労働者の非常に強いカード、権利として認められている。休暇中に呼び出されたりメール対応をしたりすることもないし、それを客が求めても通ることはない。メールを送ると「〇〇は休暇中です。◯日に戻ります」という自動返信メールが返信される。上記のようなビジネス上の不利益は客が我慢することが求められる。会社としては同僚同士でカバーし合えばいいだけなのだが、文化を変えるのはなかなか大変だ。もちろん、そこにビジネスチャンスはあるので、伸びてきている新興のベンチャーなどはこれらの不便さを解消した会社もある。頼むから1)が標準になって欲しいと思うのだが、アメリカの医療界は、こういった会社とは真逆で1)が標準である。
私が医師になった20数年前は日本では普通に3)が一般的であった。今でも規模の小さな病院や診療所では3)の対応をせざるを得ないだろう。思い起こせば、勤務時間外であっても常に呼び出される可能性があり、休暇中でも対応せねばならないような状況であった。「主治医になるということは常に呼び出されるということ」を意味した。特に重症患者の担当になるといつでも駆けつけられるように病院から半径数キロ以内にいなければならないし、飲酒も控えなければならない。何よりもおちおち眠っていられない。もちろん眠ってもいいのだが、携帯やポケベルの音に反応して覚醒しなければならない。睡眠医学的に言えば覚醒の閾値が高い「深睡眠に入ってはいけない」ことを意味する。そんなことができるのか?と思うが人間はある程度このような芸当ができるようにできている。緊張感、不安感を高めて覚醒のシステムを常にある程度オンにしておくのだ。時々高校野球の強豪校や宝塚歌劇団や自衛隊の寮生活の厳しさを紹介するときに「めざまし時計は鳴る前に消す」とか「夜間の突然の集合命令に1分以内に覚醒して集合する」などと紹介されることがあるが、いい例だ。当たり前だがそのように睡眠を浅くすると、必然的に中途覚醒は増えるし熟眠感は減る。主治医になるということはそういう状況に置かれることを意味する。私も経験したことがあるが、かなりきつい。短期間は可能だが、長期の持続は不可能だ。最近ではテクノロジーが発達してしまった(だいたいどこでもWifiが接続できる)ので海外にいてもある程度対応できるようになってしまった。そんな主治医制が全盛だった日本から米国の内科レジデンシーを始めたのだが、当時はそれこそ今で言う労働時間制限の週80時間ルール(https://www.acgme.org/globalassets/pfassets/publicationspapers/dh_dutyhoursummary2003-04.pdf参照)もなく、3―4日おきに終夜の当直があり、今と比べれば厳しい状況ではあったが、毎日勤務時間が終わればポケベルをオフにできるので私は「なんて楽なのだ!」と思った。)当直以外の日には熟睡もできるようになった。きついトレーニング期間だったが、よく眠っていたおかげで戦い抜くことができたと思っている。同時にこの「ポケベル(携帯)オフ」を実現するために、クロスカバーと言う「引き継ぎ」を行うことが表裏一体で必須であることも経験した。これは自分の担当患者を当直の研修医に午後5時以降は担当してもらうために、簡単なサマリーと急変時の指示をまとめて申し送りする作業なのだが、これを実現するためにはある複数の条件が揃う必要がある。一つは全ての主治医が標準治療を行っていて「その医者じゃないとわからない」なんて治療をしていないことである。その上で静脈ラインが抜けたら入れ直す必要があるか?、発熱したら血液培養をとる必要があるか?、D N Rの希望は?、といった急変時の指示も含めて申し送りをする。この申し送りは引き受ける方も責任重大なので真剣なディスカッションする。すなわち、自分の患者の診療を毎日同僚にプレゼンすることになるので標準治療から逸脱したことはできなくなるし、もしも少しガイドラインが決まっていないようなエビデンスの弱い治療をしている時は、ちゃんと正当化できる理由を説明できるように準備しておかねばならない。このおかげで常に「同僚に正当性を説明できるか?」と言う意識が身に付いた。主治医はいるのだが、グループもしくは診療科全体で患者の情報を共有し、「ある医者が責任をもつ患者」ではなく「診療科全体が責任をもつ患者」と言う意識が生まれた。これは研修医の申し送りだが、指導医もグループを作っていて交代で休暇を取れるようにしていた。患者も担当医が休暇に行くことに対し「ドクターにも休暇が必要だよね。良い休暇を!」と言うのには驚いた。これは他にもアメリカで臨床トレーニングを受けた医者が何人もいろいろな媒体で証言しているので、文化的なテンプレートなのだと思っている。このクロスカバーを成立させるには、1)医者が標準治療を行う、2)グループで情報を常に共有している、3)患者が休暇の必要性を認識している
ことが必要で、それが成立している社会というのはやはり成熟していると思うし、働き方改革はそこを目指すべきなのだと思う。身体が病院に物理的に存在しないことは休息の必要条件にすぎず、クロスカバーを前提にして完全に呼び出しがない状態があって初めて真の休息と言える。
「そんなクロスカバーをするような人員数を確保できない」という声が聞こえてきそうだが、これを目指すならば一つの病院ではなく、地域全体で実現することも考えればいいと思う。そのためには電子カルテの共有や、院外からのアクセスなどハードルは色々ある。それこそトップダウンでないと決まらないと思うが、目指す場所に向けて少しずつ進んで行けば良いと思う。実際にこれが実現されている環境での勤務をしてしまうと、クロスカバーのない環境では勤務できなくなる。勤務時間というわかりやすいルールを定めるのは働き方改革の第一歩だと思うのだが、クロスカバーのない自宅待機は決して真の意味での休息ではないことを知ってもらいたい。